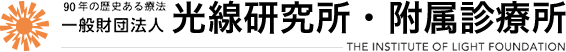- 可視総合光線療法を知る
- 研究報告
研究報告
年別アーカイブ
可視総合光線療法研究会
2025年10月12日(日)開催
- ①『熱ショックタンパク(HSP)と可視総合光線療法』
- ②『のう胞性疾患に対する可視総合光線療法』
2025年8月10日(日)開催
- ①『抗ガン剤の副作用を軽減し、闘病生活をサポートする可視総合光線療法』
- ②『線維筋痛症による痛みが光線治療で緩和している症例』
2025年6月8日(日)開催
- ①『女性の更年期障害に対する可視光線療法』
- ②『変形性膝関節症に対する可視総合光線療法』
2025年4月13日(日)開催
- ①『高齢者に多い四大骨折に対する可視光線療法』
- ②『風邪・インフルエンザの予防に対する可視総合光線療法』
2025年2月9日(日)開催
- ①『疲労に対する可視光線療法』
- ②『緑内障の進行が可視総合光線療法で抑えられている症例』
2024年12月1日(日)開催
- ①『ガットフレイル・機能性ディスペプシアなど胃腸の不調に対する可視光線療法』
- ②『ぎっくり腰(急性腰痛症)に対する可視総合光線療法』
2024年10月13日(日)開催
- ①『一酸化窒素(NO)と可視総合光線療法』
- ②『放射線治療後の副作用に対する可視総合光線療法』
2024年8月11日(日)開催
- ①『生体リズムの調節と可視総合光線療法』
- ②『良性発作性頭位めまい症に対する可視総合光線療法』
2023年12月3日(日)開催
- ①『肝胆膵疾患に対する可視総合光線療法』
- ②『首下がり症に対する可視総合光線療法』
2023年10月8日(日)開催
- ①『細胞間リンパ液と可視総合光線療法』
- ②『アイフレイルに対する可視総合光線療法』
- ③『顔面神経麻痺(ベル麻痺・ハント症候群)に対する可視総合光線療法』
2023年8月13日(日)開催
- ①『過労に対する可視総合光線療法』
- ②『夫源病・妻源病に対する可視総合光線療法』
2023年4月8日(土)開催
2023年2月23日(木)開催
- ①『腸疾患の便秘、過敏性腸症候群、潰瘍性大腸炎に対する可視総合光線療法』
- ②『腰痛改善に大切な腹側の筋肉と可視総合光線療法』
2022年11月20日(日)開催
- ①『心不全とその症状に対する可視総合光線療法』
- ②『唾石症に対する可視総合光線療法』
2022年10月8日(土)開催
- ①『ミトコンドリアを活性化させる可視総合光線療法』
- ②『創傷と可視総合光線療法』
2022年8月は、コロナ禍のため中止
- 8月 ①『可視総合光線療法における治療用カーボン変更による改善例』
- 8月 ②『後縦靭帯骨化症の症状改善効果がみられた症例』
2022年6月12日(日)開催
- ①『すこやかな妊娠と出産をサポートする可視総合光線療法』
- ②『嗅覚障害が回復した光線治療症例』
2022年2月、4月は、コロナ禍のため中止
- 2月 ①『扁桃炎・副鼻腔炎に対する可視総合光線療法』
- 2月 ②『下肢の症状改善に肩こりの治療が有効だった症例』
- 4月 ①『胃食道逆流症(逆流性食道炎)に対する可視総合光線療法』
- 4月 ②『オーラルフレイルのケアと可視総合光線療法』
2021年12月12日(日)開催
- ①『変形性股関節症に対する可視総合光線療法』
- ②『光線療法との併用で透析療法が長年安定して継続可能な症例』
- ③『皮膚の痒みと可視総合光線療法』
2021年2月、4月、6月、8月、10月は、コロナ禍のため中止
- 2月 ①『新型コロナウイルス感染症に対する可視総合光線療法(その2)』
- 2月 ②『慢性前立腺炎/慢性骨盤痛症候群に対する可視総合光線療法』
- 2月 ③『半月板損傷による膝痛が光線療法で改善した症例』
- 4月 ①『可視総合光線療法によりガンの経過が良好な5症例とその解説』
- 4月 ②『可視総合光線療法で肝機能が改善した症例』
- 6月 ①『顔面神経麻痺に対する可視総合光線療法』
- 6月 ②『薬疹が光線療法で改善した症例』
- 8月 ①『加齢性の慢性炎症と可視総合光線療法』
- 8月 ②『首回りの光線照射で思わぬ効果がみられた症例』
- 10月 ①『皮膚の痒みと可視総合光線療法』
- 10月 ②『可視総合光線療法で圧迫骨折の予後が良好な症例』
2020年12月13日(日)開催
- ①『新型コロナウィルス感染症と可視総合光線療法(その1)』
- ②『高齢者の健康を支える可視総合光線療法』
- ③『心臓弁膜症に対する可視総合光線療法』
- ④『手や顔のかぶれ(接触皮膚炎)が可視総合光線療法で改善した症例』
2020年4月、6月、8月、10月は、コロナ禍のため中止
- 4月 ①『眼病に対する可視総合光線療法(その2)』
- 4月 ②『就寝中に起こりやすいこむら返りに対する光線治療』
- 6月 ①『狭心症に対する可視総合光線療法』
- 6月 ②『頸椎や腰椎術後症状改善がなかったのが光線療法で改善した症例』
- 8月 ①『うつ病が原因の痛みと可視総合光線療法』
- 8月 ②『巣ごもり生活で要注意 便秘・筋力低下・むくみに対する可視総合光線療法』
- 10月 ①『高齢者の健康を支える可視総合光線療法』
- 10月 ②『手や顔のかぶれ(接触皮膚炎)が可視総合光線療法で改善した症例』
2020年2月9日(日)開催
- ①『眼病に対する可視総合光線療法(その1)』
- ②『悪化した下肢静脈瘤が光線療法で改善した症例』
- ③光線治療例報告
2019年12月9日(日)開催
- ①『頭頚部ガンに対する可視総合光線療法』
- ②『余命宣告を越え延命しているガンの2症例』
- ③光線治療例報告
2019年10月13日(日)開催
- ①『痛みの原因となる異常血管と可視総合光線療法』
- ②『顎関節症に対する光線療法で改善がみられた症例』
- ③光線治療例報告
2019年8月11日(日)開催
- ①『意欲や活力を取り戻す可視総合光線療法』
- ②『石灰沈着による肩痛が光線療法で改善した症例』
- ③光線治療例報告
2019年6月9日(日)開催
- ①『蜂窩織炎に対する可視光線療法』
- ②『進行胃ガン、末期ガンでも光線療法で経過が良好な症例』
- ③光線治療例報告
2019年4月14日(日)開催
- ①『手指や足趾の血行不良と可視総合光線療法』
(閉塞性動脈硬化症・バージャー病・SLEによる手足の壊死) - ②『痛風(尿酸値上昇の抑制)に対する可視総合光線療法』
- ③光線治療例報告
2019年2月10日(日)開催
- ①『大腸疾患に対する可視総合光線療法(大腸ガン・大腸ポリープ・大腸憩室症について)』
- ②『頸椎の異常による症状が光線療法で改善した症例(頚椎症・ストレートネック・頸椎ヘルニア)』
- ③光線治療例報告
2018年12月9日(日)開催
- ①『神経疾患患者の骨折予防と可視総合光線療法』
- ②『体内に医療器具が入っている場合の可視総合光線療法』
- ③光線治療例報告
2018年10月14日(日)開催
- ①『自律神経バランスに対する可視総合光線療法』
- ②『発症早期の突発性難聴に対する可視総合光線療法』
- ③光線治療例報告
2018年8月12日(日)開催
- ①『口の渇き(ドライマウス)に対する可視総合光線療法』
- ②『痔に対する可視総合光線療法』
- ③光線治療例報告
2018年6月10日(日)開催
- ①『睡眠に対する可視総合光線療法』
- ②『前立腺腫瘍マーカーPSAが光線療法で改善している症例』
- ③光線治療例報告
2018年4月8日(日)開催
- ①『機能性身体症候群に対する可視総合光線療法』
- ②『顔面打撲に対する可視総合光線療法』
- ③光線治療例報告
2018年2月11日(日)開催
- ①『難病に対する可視総合光線療法(その2)』
- ②『肩に障害を引き起こしやすい不良姿勢と可視総合光線療法』
- ③光線治療例報告
2017年12月10日(日)開催
- ①『難病に対する可視総合光線療法(その1)』
- ②『ペット(動物)に対する可視総合光線療法』
- ③光線治療例報告
2017年10月8日(日)開催
- ①『歯周病と可視総合光線療法』
- ②『子宮頸部異形成に対して光線で効果が見られた症例』
- ③光線治療例報告
2017年8月13日(日)開催
- ①『可視総合光線療法でステロイドの減薬・副作用軽減に効果が見られた症例』
- ②『捻挫に対する可視総合光線療法』
- ③光線治療例報告
2017年6月11日(日)開催
- ①『交通事故傷害に対する可視総合光線療法』
- ②『光線治療によるガンの放射線治療副作用の改善例』
- ③光線治療例報告
2017年4月9日(日)開催
- ①『骨粗鬆症と可視総合光線療法』
- ②『高齢者の肩腱板損傷に光線治療が効果的であった症例』
- ③光線治療例報告
2017年2月12日(日)開催
- ①『健康長寿を支える可視総合光線療法』
- ②『可視総合光線療法による風邪の後遺症に対する改善例』
- ③光線治療例報告
2016年12月11日(日)開催
- ①
- ②『膝の筋力トレーニングに対する可視総合光線療法』
2016年10月9日(日)開催
- ①
- ②『疲労回復に対する可視総合光線療法』
2016年8月14日(日)開催
- ①
- ②『腱鞘炎と手根管症候群に対する可視総合光線療法』
2016年6月12日(日)開催
- ①
- ②『加齢に伴って増える目の変化や病気に対しての光線療法』
2016年4月10日(日)開催
- ①
- ②『腸閉塞の予防に効果が見られた症例』
2016年2月14日(日)開催
- ①
- ②『爪の異常に対する可視総合光線療法の治療例』
2015年12月13日(日)開催
- ①
- ②『寒い季節に起こる皮膚トラブルに対する可視総合光線療法』
2015年10月11日(日)開催
- ①
- ②『手指・手首の骨折後の運動障害に効果が見られた症例』
2015年8月9日(日)開催
- ①
- ②『いぼに対する可視総合光線療法』
2015年6月14日(日)開催
- ①
- ②『梅雨に悪化しやすい水虫(白癬菌)に対する可視総合光線療法』
2015年4月12日(日)開催
- ①
- ②『可視総合光線療法による花粉症の改善例』
2015年2月8日(日)開催
- ①
- ②『可視総合光線療法による皮膚のかさつきの改善例』
2014年12月14日(日)開催
- ①
- ②『バセドー病の抗甲状腺薬中止に効果が見られた症例』
2014年10月12日(日)開催
- ①
- ②『可視総合光線療法による抗ガン剤での手足のしびれ・痛みの改善例』
2014年8月10日(日)開催
- ①
- ②『外反母趾による痛みの改善が見られる症例』
2014年6月8日(日)開催
- ①
- ②『顔面神経麻痺(ベル麻痺)に対する可視総合光線療法』
2014年4月13日(日)開催
- ①
- ②『光線療法による手足の末梢神経麻痺の改善例』
2014年2月9日(日)開催
- ①
- ②『眼・鼻・口腔内術後の可視総合光線療法(白内障・副鼻腔炎・インプラント)』
2013年12月8日(日)開催
- ①
- ②『不妊症の可視総合光線療法』
2013年10月13日(日)開催
- ①
- ②『長引く足裏の痛みに光線療法の効果がみられた症例』
2013年8月11日(日)開催
- ①
- ②『月経困難症と可視総合光線療法』
2013年6月9日(日)開催
- ①
- ②『高齢者に多い腰椎すべり症と可視総合光線療法』
2013年4月14日(日)開催
- ①
- ②『高齢者の足のむくみと可視総合光線療法』
2013年2月10日(日)開催
- ①
- ②『見た目が気になる唇の荒れと可視総合光線療法』
2012年12月9日(日)開催
- ①
- ②『糖尿病網膜症の可視総合光線療法』
2012年10月14日(日)開催
- ①
- ②『可視総合光線療法で皮膚・血管の硬化が抑えられた症例』 = 繰り返し注射針を刺す場合 =


臨床研究報告
令和5年度研究報告 『体の麻痺に対する可視総合光線療法』
体の麻痺には全く自由がきがなくなる状態と少し動がせる状態があり、脳・脊髄からなる中枢神経、中枢神経と体の各器官を結石末梢神経、神経と筋肉の接合部や筋肉の異常などが原因で起こります。麻痺の原因となる主な疾患には、脳梗塞や脳出血、ウイルス性脳炎などがあり、脳の中枢神経が障害を受けることで体の片側に麻痺が生じます。末梢神経が圧迫されて体の片側に麻痺が起こる疾患には、顔面神経麻庫、僥骨神経麻痺、手根管症候群、変形性腰椎症、腰椎椎間板ヘルニアなどがあります。また、末梢神経の障害によって体の片側に限らず、さまざまな部分に麻痺が起こる疾患には、自己免疫病の重症筋無力症などがあります。麻痺が生じると障害部位によっていろいろな症状がみられ、日常生活にさまざまな支障が出てきます。本光線療法は光・熱エネルギーを体に補給し、冷えや血行の改善、ビタミンD産生など介して神経麻痺を回復させます。
令和5年度は、神経麻痺患者に対する可視総合光線療法の有用性を体温測定、加速度脈波からみた血行状態、握力などを測定しその有用性を検討しました。 具体的な不調の内容を症状別にみますと、男女とも腰痛、肩こり、関節痛などが多く、骨・関節疾患の対策が重要となります。 光線療法のため当附属診療所を受診する患者の中で痛みを訴えている人が多くみられます。本療法は光・熱エネルギーを補給し、冷えや血行改善、ビタミンD産生などを介し鎮痛効果を発揮することで骨、関節疾患者にも広く使われます。 今回は、骨・関節疾患に対する可視総合光線治療の有用性を、体温測定、加速度脈からみた血行状態、血圧、握力などを測定し症状の経過とともにその有用性を検討します。
令和4年度研究報告 『高齢化社会における骨・関節疾患と可視総合光線療法』
本邦は超高齢化社会で、令和2年9月15日現在の65歳以上の人口は、3617万人、総人口に占める割合が28.7%と世界で最も高齢化が進行しています。この高齢化社会で解決すべき重要な課題は、健康寿命の延伸、生活の質(QOL)の追及です。平成28年の国民生活基礎調査によれば、有訴者は305.9/千人で、国民の約3人に1人は何らかの体調不調を訴えていることになります。有訴者率を性別でみると男性が271.9、女性が337.3と女性に高く、年齢が高くなるにしたがい上昇し、80歳以上では520.2とほぼ2人に1人となっています。高齢化社会の進行は、有訴率を引き上げることにつながっています。
具体的な不調の内容を症状別にみますと、男女とも腰痛、肩こり、関節痛などが多く、骨・関節疾患の対策が重要となります。光線療法のため当附属診療所を受診する患者の中で痛みを訴えている人が多くみられます。本療法は光・熱エネルギーを補給し、冷えや血行改善、ビタミンD産生などを介し鎮痛効果を発揮することで骨、関節疾患者にも広く使われます。今回は、骨・関節疾患に対する可視総合光線治療の有用性を、体温測定、加速度脈からみた血行状態、血圧、握力などを測定し症状の経過とともにその有用性を検討します。
令和3年度研究報告 『女性の病気と可視総合光線療法(2)』
ビタミンDの欠乏・不足が世界的にも大きな問題です。本邦での研究では、80%以上の女性がビタミンD不足あるいは欠乏の状態で、50歳以上(平均64.1歳)の女性で血中ビタミンDが30ng/ml以上であるのはわずか10%で、約半数がビタミンD欠乏であることが報告されています。ビタミンD欠乏症は骨粗鬆症、脊椎圧迫骨折など骨の代謝異常のみならず、近年では2型糖尿病や心血管疾患、高血圧、ガン、感染症、自己免疫疾患などの発症リスクを上昇させることから、その重要性が注目されています。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)とビタミンDの関連が近年注目され、免疫機能を高める作用があるビタミンDは新型コロナウイルスの感染予防や重症化予防との関連を示す論文が数多く報告されています。これらの論文から、人体においてビタミンD産生作用がある日光浴による感染症予防(ビタミンD不足や光線不足の解消)が新型のウイルスの感染や重症化予防において証明されたことになります。太陽光と類似のプルスベクトルの光線を利用する可視総合光線療法と関係する論文報告は興味深いものです。
今年度は、前年度に引き続きビタミンD欠乏・不足と関連する腰椎圧迫骨折・骨粗鬆症、左肩痛・左膝痛・腰痛・骨粗鬆症、手首の骨折、骨折後の手の痛み・浮腫、変形性膝関節症・骨粗鬆症、子宮内膜症・卵巣のう腫、季節性感情障害・易疲労感・うつ傾向、緊張型頭痛、尿失禁、肛門痛・直腸部痛、関節リウマチ、アトピー性皮膚炎、尋常性乾癖、掌蹠膿疱症の光線治療例について、血行状態、血圧、握力、体温、骨量などの変動とともに考察を加え、女性においてビタミンD不足、光線不足と関連する生活習慣病などに対する本療法の有用性を検討し、新型コロナウイルス感染症についても併せて検討しました。
令和2年度研究報告 『女性の病気と可視総合光線療法』
女性の社会進出、核家族化、家事労働時間の短縮など女性をとりまく社会環境は変化し、女性のライフサイクル・ライフスタイルも大きく変化しています。女性に特異的な病気とヘルスケアの重要性が増加しています。働く女性は退職までに閉経を迎え、様々な疾患リスクが上昇しており、代表的疾患として骨粗鬆症があります。
女性の健康管理の背景には、ライフステージに関連した特有の疾患とメンタルヘルスがあり、その多くにはビタミンDが関係しています。男性と違い女性は閉経後よりビタミンDと関連する疾患リスクが上昇してきます。女性が健康で働き続けるためには、閉経前からビタミンDに対する知識、関心、対策が大切です。ビタミンD・カルシウム・光線の不足が疾患に至る機序として、骨からカルシウムが溶け出す(骨粗鬆症)→組織にカルシウムが沈着する→大動脈では石灰化が起こる(動脈硬化)→糖尿病、高血圧症、心筋梗塞症、脳卒中、脂質異常症、ガンなど、と考えられます。
古代からの日光浴とその応用である光線療法は、皮膚でビタミンDが産生されたことによりもたらされる基本的な健康法です。充足したビタミンDの状況が日々の健康管理に重要です。ビタミンD欠乏や不足を是正するために積極的な日光暴露の習慣が2型糖尿病の発症リスクを30%低下させることや、ビタミンD投与で高血圧及び動脈硬化が減少したという研究が多くあります。太陽光と同種の連続フルスペクトル光線を利用する可視総合光線療法の治療例からも、骨粗鬆症、糖尿病、高血圧、脂質異常症、血管障害、ガンなどの疾患に対し、本光線療法は熱エネルギーを補給することで冷えた身体を温めて血行を改善し、一方、光エネルギーの作用によりビタミンD産生を促すとともに、自律神経・内分泌系、免疫系を刺激し、体調を調整し、睡眠、食欲、便通などの生活の質を良好にして抗病力を高めて病気を回復させます。可視総合光線療法は予防医学という観点からも食生活や日常生活など、働く女性の背景、健康状況を把握し、女性におけるビタミンD欠乏や不足状態を改善し充足させることから、将来的な疾患負担の軽減並びに医療費軽減にもつながる有益な健康療法と考えます。
令和1年度研究報告 『眼疾患に対する可視総合光線療法の有用性の調査研究』
本邦では、子供の近視の原因が日光不足であることを示す研究が多く報告されている。眼は物を見るという重要な機能以外に、眼から入った光線はメラトニン分泌などの調節を介して生体リズムを調整する作用があり、睡眠、自律神経系、ホルモン分泌、免疫系の調節などに大きく影響する。これからの人生は百年時代といわれ、長寿化を見越した人生を生き抜くためには『眼の健康』はとても重要である。今回は眼疾患に対する可視総合光線療法について調査し光線療法の有用性について検討した。
眼疾患に対する可視総合光線療法は、本療法に用いる光と熱エネルギ-を補給することにより、止血吸収作用、抗炎症作用、免疫力強化など創傷治癒力を高めて多くの眼疾患の傷ついた組織を修復し、眼の生理機能を回復させて視力上昇の促進や視力低下の予防に効果がある。これらの結果から、可視総合光線療法は眼疾患の治療や予防にも役立つ有用な療法であると考えられる。 眼疾患としては、以下の調査例などがあった。
- ・白内障、緑内障、飛蚊症
- ・糖尿病性網膜症、網膜剥離、網膜裂孔
- ・加齢黄斑変性症、黄斑前膜
- ・眼底出血、網膜中心静脈閉塞症
平成30年度研究報告 『不妊症に対する光線療法の有用性の調査研究』
本邦では、夫婦の10組に1組が不妊症といわれている。光線療法は、これまで多くの不妊症の患者の受胎、妊娠継続、出産に寄与するとともに光線治療の継続は安産、産後の良好な体調回復にもつながることが示されてきた。今回の研究では、出産経験のない不妊症患者を対象に、光線療法開始から出産までの期間、出産時の年齢、出産月による出産児の体重の違い、不妊の原因と考えられる疾患の有無、体外受精や帝王切開の有無など、光線療法が妊娠、出産児に与える影響について調査し光線療法の有用性について検討した。
不妊の原因としては、以下のものなどがあり、原因がはっきり分からないものもあった。
- ・子宮内膜症、卵巣のう腫
- ・不育症
- ・子宮筋腫
- ・橋本病
- ・卵巣機能不全
- ・高プロラクチン血症・その他を含むホルモン異常
平成29年度研究報告 『甲状腺疾患に対する可視総合光線療法』
本邦における甲状腺疾患の罹患数は約790万人で、そのうち治療が必要な患者は約240万人と推計されている。しかしながら、実際に治療を受けているのは厚生労働省平成26年患者調査では約45万人と報告されており、未治療の患者が多く存在していることが指摘されている。甲状腺ホルモンは新陳代謝、エネルギ-代謝に関わる重要なホルモンであり、その増減はからだに大きな影響を与える。 可視総合光線療法は甲状腺疾患患者にも多く利用されている。本症患者では多くがビタミンD不足であり、自己免疫異常も関与していることから、平成29年(2017年)度は、甲状腺疾患に対する可視総合光線療法の有用性について文献的考察を含めて検討した。
- ・バセドウ病
- ・橋本病
- ・甲状腺ガン
- ・単純性びまん性甲状腺腫
平成28年度研究報告 『難病など希有な疾患と可視総合光線療法』
可視総合光線療法は、疼痛、腫脹などの炎症性疾患、外傷や手術創による傷痕、関節リウマチなどの自己免疫疾患、皮膚病、眼病、ガンなど多くの疾患に利用されている。近年は、各種ガンをはじめ難治性疾患や難病で当附属診療所を受診する患者も多くみられる。そこで平成28(2016)年度は、以下の疾患や指定疾患に対する可視総合光線療法の成果をまとめて検討した。
なお、今回はガンの治療例は除外してある。
- ・球脊髄性筋萎縮症(指定難病1)
- ・重症筋無力症(指定難病11)
- ・慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー (指定難病14)
- ・遠位型ミオパチー(指定難病30)
- ・好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(指定難病45)
- ・原発性抗リン脂質抗体症候群(指定難病48)
- ・成人スチル病(成人スティル病)(指定難病54)
- ・潰瘍性大腸炎(指定難病97)
- ・脊髄空洞症(指定難病117)
- ・類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。)(指定難病162)
- ・「好酸球性筋膜炎」・「菌状息肉症」・「フィッシャ-症候群」
- ・「コルネリア・デランゲ症候群」・「網状皮斑」・「複合性局所疼痛症候群」
平成27年度研究報告 『不妊症と可視総合光線療法』
本邦では、夫婦の10組に1組が不妊症といわれている。産婦人科的には、「定期的な性生活を送り、ある一定期間避妊などを行わず性生活を行っているにもかかわらず、2年以上妊娠しない場合」が不妊症とされていた。しかし、平成25~26年度生殖・内分泌委員会生殖医療リスクマネージメント小委員会の報告では、「生殖年齢の男女が妊娠を希望し,ある一定期間,避妊することなく通常の性交を継続的に行っているにもかかわらず、妊娠の成立をみない場合を不妊という.その一定期間については1年というのが一般的である。なお、妊娠のために医学的介入が必要な場合は期間を問わない。」と変更された。
健康な男女が結婚して通常の性生活を営んでいる場合、1年以内に約80%、2年以内では約90%が妊娠している。また、不妊症の疑いがない男女が、排卵日に性交渉をしても妊娠確率は20%程度であり、妊娠は意外に簡単でないことがわかる。近年は女性の晩婚化傾向やキャリア形成指向などもあり、30歳代後半以降の妊娠は生殖補助医療による治療を行ってもますます難しくなっている。これは、高年齢になるにつれて、子宮内膜症や子宮筋腫などの妊孕性(にんようせい)を障害する病態が出現する率が高まるとともに、卵・卵胞の発育を障害する病態の頻度が高くなり、さらに卵・卵胞の質が障害されてくることによると考えられる。
光線療法は、これまで多くの不妊症の患者の受胎、妊娠継続、出産に寄与するとともに光線治療の継続は安産、産後の良好な体調回復にもつながることが示されてきた。今回の研究では、出産経験のない不妊症患者を対象に、光線治療開始から出産までの期間、出産時の年齢、出産月による出産児の体重の違い、不妊の原因と考えられる疾患の有無、体外受精や帝王切開の有無など、光線療法が妊娠、出産児に与える影響について調査し光線療法の有用性について検討した。
平成26年度研究報告 『頭痛に対する可視総合光線療法の有用性』
頭痛は日常診療のなかでもよく遭遇する疼痛疾患で、繰り返し起こる慢性的な頭痛に悩む人は、日本で約三千万人いると言われ、日本における15歳以上の頭痛有病率(39.6%)の中で緊張性頭痛の有病率が22.3%と最も高く、ついで片頭痛が8.4%と言われている。 しかし、病院で診察を受けている人はこのうち3割程度で、大半は体質だと諦め、市販薬に頼ったり我慢をしているようである。
当所でも頭痛で受診される患者は多く、光線療法の深部温熱効果は緊張性頭痛に、光化学作用によるビタミンD産生、カルシウム代謝の改善は月経時片頭痛に効果が見られている。 頭痛患者の多くはビタミンD不足状態が指摘されていることから、頭痛患者全般に深部温熱作用やビタミンD産生作用など多彩な作用を有する光線療法は薬剤と違い副作用の少ない治療法であると考えられるので、頭痛に対する光線療法の有用性について検討した。
平成25年度研究報告 『C型慢性肝炎の光線治療の有用性について』
近年、ペグインタ-フェロン+リバビリン併用療法中の難治性C型慢性肝炎患者において、ビタミンDを投与して血中ビタミンD濃度を改善させると、現在行われている新しい抗ウイルス薬+ペグインタ-フェロン+リバビリン3者併用療法に劣らない効果がみられると報告されている。
日本人の多くはビタミンD不足状態であると報告されていることから、C型慢性肝炎の病院治療時に光線治療を併用してビタミンD不足を是正することは重要と考えられる。
そこで、当所でのC型慢性肝炎の光線療法の有用性について検討した。
平成24年度研究報告 『乳ガン手術時期と予後』
ガン患者の予後は診断時期や手術時期と関連するという報告がある。季節による日照時間の違いから皮膚で産生されるビタミンD量は増減し、血中ビタミンD濃度の高低により免疫機能にも高低がみられ、さらにガン患者やガンに羅患してもガンを抑制する抵抗力にも影響を及ぼし予後に影響する(ビタミンD仮説)。
そこで、光線療法の有用性の一環として、ガン患者とくに患者数が多い乳ガン患者を対象に、手術時期と予後につき当附属診療所を受診した乳ガン患者の中から234例を対象に、季節別に各年代の術後の経過を比較検討した。
平成23年度研究報告 『乳ガン患者の光線療法の継続の意義』
今回は、具体的に女性のガンの第1位を占める乳ガン患者について可視総合光線療法の継続意義を検討した。当財団附属診療所を受診する乳ガン患者は多く、手術に対する不安や術後の傷の痛みや抗ガン剤、ホルモン剤、放射線治療の副作用の不安などのさまざまな問題を抱えておりこれらに対する光線療法の作用及び効果に対する期待は大きいことから、光線療法の継続の意義を検討した。
平成22年度研究報告 『ガン患者の光線療法についての基礎研究』
我が国では1981年から現在までガンが最大の死因となっている。近年では、日本人の3人に1人はガンによって亡くなっている。とくに、40歳代や50歳代などの働き盛りの世代では、死因の半数近くをガンが占めている。 可視総合光線療法を実践している当附属診療所においても来診するガン患者は多い。ガン患者は、ガン自体の症状に加え、ガン治療に伴う手術、化学療法、放射線療法などの副作用の心配、さらにガン治療中の不眠、不安、抑うつ気分などの精神的負担など多くの問題をかかえている。当所を受診するガン患者の多くは、病院治療に対する不安を強く訴えている状況がみられる。
光線療法は、病院治療だけでは対処できない術後の体調回復促進、化学療法の副作用軽減、ビタミンD産生による免疫調節などに寄与することができるとともに、光線療法でからだを温めることことはガン患者の精神的動揺を安定させ、食欲・便通・睡眠など体調管理に少なからず期待できると考えられることから、光線治療の総合的な有効性ついて検討した。
上記以前の臨床研究報告内容
- ●平成21年度研究報告 『筋力の衰えや転倒に対する光線療法の有効性その2』
- ●平成20年度研究報告 『筋力の衰えや転倒に対する光線療法の有効性』
- ●平成19年度研究報告 『皮膚感染症に対する光線療法の有効性その2』
- ●平成18年度研究報告 『皮膚感染症に対する光線療法の有効性』
- ●平成17年度研究報告 『長期間光線療法を継続している治験例と自律神経バランスを検討した治験例』
- ●平成16年度研究報告 『長期間光線療法を継続している治療例』
- ●平成15年度研究報告 『自己免疫病・難病に対する可視総合光線療法その2』
- ●平成14年度研究報告 『自己免疫病・難病に対する可視総合光線療法』
- ●平成13年度研究報告 『可視総合光線療法の骨量に及ぼす影響その2』
- ●平成12年度研究報告 『可視総合光線療法の骨量に及ぼす影響』
- ●平成11年度研究報告 『光線治療中で骨密度の測定を1年以上観察できた15例に対する検討』
- ●平成10年度研究報告 『光線療法の骨密度に及ぼす影響』
- ●平成 9年度研究報告 『光線療法におけるビタミンⅮとがん治療について』
平成8年度研究報告以前のものは省略